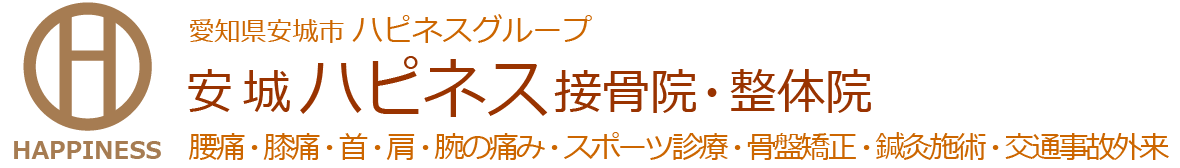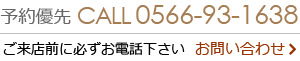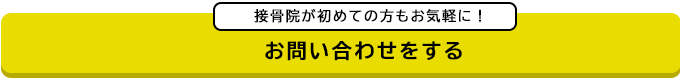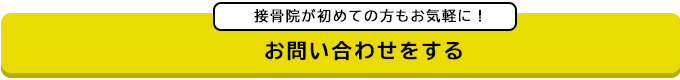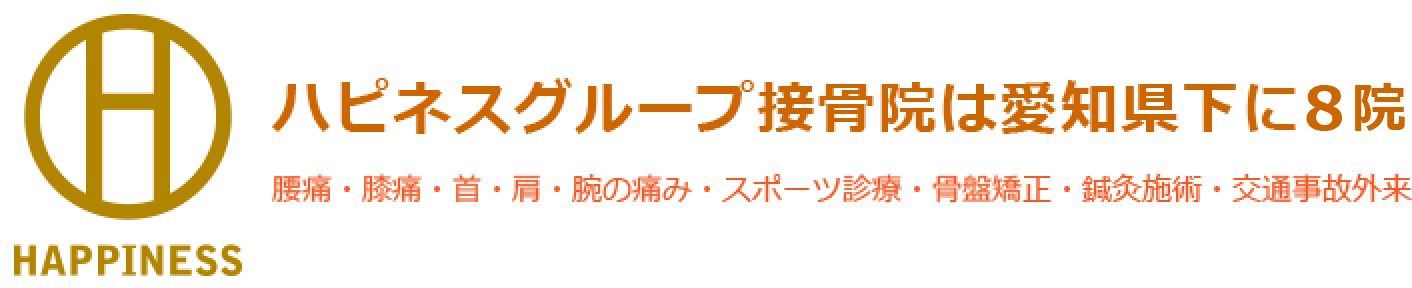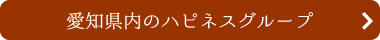こんにちは!安城ハピネス接骨院です。
肘の痛みは、スポーツをしている方だけでなく、日常生活や仕事の動作の積み重ねによっても起こります。「使いすぎかな」と放置してしまうと、痛みが長引いたり、他の部位へ負担が広がることもあるため注意が必要です。ここでは、接骨院でよく見られる肘の痛みの代表的な症例についてご紹介します。
① テニス肘(上腕骨外側上顆炎)
肘の外側に痛みが出る症例で、ラケット競技をしていない方にも多く見られます。
原因は、手首を反らす動作の繰り返しや、パソコン作業、家事などによる前腕筋の使いすぎです。
症状としては、物をつかむ・持ち上げる・ドアノブを回す動作で肘の外側に痛みが出ます。
② ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)
肘の内側に痛みが出る症例です。
原因は、手首を曲げる動作や強い握力を必要とする動作の繰り返し。ゴルフ以外にも、重い物を持つ作業や育児で起こることがあります。
症状は、肘の内側の痛みや、前腕にかけての違和感、力が入りにくい感覚です。
③ 肘部管症候群
肘の内側を通る尺骨神経が圧迫されることで起こる症例です。
症状として、小指や薬指のしびれ、細かい動作がしにくくなるなどがみられます。長時間肘を曲げた姿勢や、肘をつく癖が原因となることが多いです。
④ 野球肘
成長期の学生に多く見られる症例で、投球動作の繰り返しによって肘に過度な負担がかかります。
症状は、投球時の痛み、肘の曲げ伸ばしがしにくいなど。放置すると骨や軟骨に影響が出るため、早期対応が重要です。
⑤ 滑液包炎(肘頭滑液包炎)
肘を頻繁につく動作や、転倒などの外傷によって起こります。
症状は、肘の先端が腫れて熱を持ち、押すと痛むことが特徴です。日常の姿勢や肘の使い方の見直しが必要になります。
肘の痛みは「肘だけ」が原因とは限りません
肘の痛みは、手首や肩、姿勢の乱れが影響しているケースも多く見られます。特に、肩や背中の動きが悪いと肘に負担が集中し、症状が長引きやすくなります。
接骨院では、
・肘周囲の炎症や筋緊張の評価
・肩、手首、姿勢を含めた全体のバランス確認
・日常動作やスポーツ動作の指導
を行い、再発しにくい身体づくりを目指します。
まとめ
肘の痛みには、テニス肘やゴルフ肘、神経症状を伴うものなど、さまざまな症例があります。「そのうち治る」と我慢せず、違和感の段階でケアすることが大切です。肘の痛みが続く場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
接骨院・整体院が初めての方へ
初めて接骨院や整体院に行く場合、どのような流れかわからず不安ではないでしょうか?
ご来店からご退室の流れ
❶ご予約・ご来店
❷問診票記入
❸問診
❹触診・検査・施術提案
❺各種施術
❻症状説明・指導
❼お会計・お見送り
安城ハピネス接骨院・整体院
愛知県安城市住吉町荒曾根1-244
0566-93-1638
#安城市ギックリ腰
#安城市接骨院情報
#安城市ハイボルテージ治療
#安城市骨盤矯正
#安城市テーピング指導
#安城市運動アドバイス
#安城市ハピネス接骨院